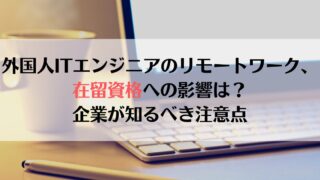外国人ITエンジニアのリモートワーク|在留資格の注意点と企業の対応策
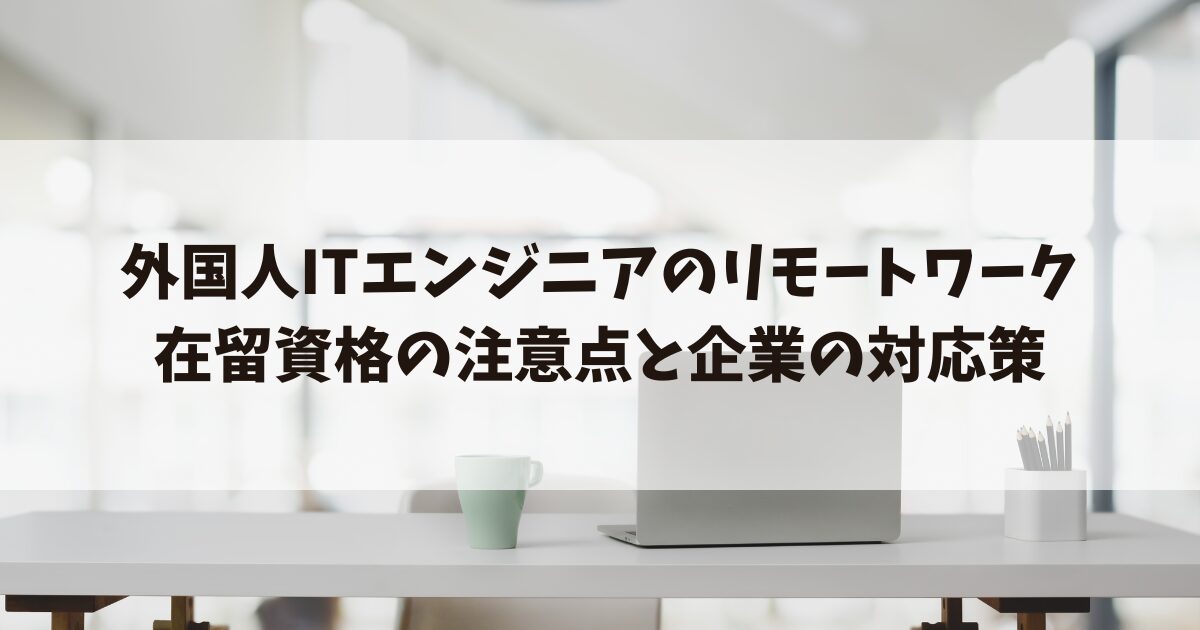
外国人ITエンジニアの雇用は、多くの日本企業にとって重要な成長戦略となっています。コロナ禍を経て働き方の選択肢として定着したリモートワークは、企業の採用力を高める一方、在留資格(ビザ)の観点では新たな論点も生んでいます。
本編では、外国人エンジニアが取得する代表的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」を軸に、国内・海外でのリモートワークにおける法的な注意点と、企業が講じるべき具体的な対応策を専門家の視点から解説します。
こちらの記事ではより詳細に説明をしています。是非ご確認ください。
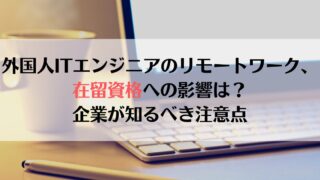
在留資格とリモートワークの基本原則
まず大前提として、全ての在留資格は「日本国内で行う活動」に対して許可されます。従来、その活動の拠点は企業のオフィスと見なされてきました。しかしリモートワークでは、従業員の自宅なども実質的な「活動拠点」となります。
ここで重要なのは、入国管理局の視点です。行政書士会が主催した研修会で、東京出入国在留管理局の審査官は「リモートワークであることのみを以て不許可にすることはない」と説明されました。審査で問われるのは、勤務形態そのものではなく、「在留資格で許可された活動が、企業の適切な管理下で、実態としてきちんと行われているか」という点です。
つまり、企業側がリモート環境下の従業員に対する労務管理や指揮命令の仕組みを整備し、それを客観的に証明できるかどうかが、ビザ審査の鍵となります。
【国内編】日本国内でのリモートワークで企業が整備すべきこと
国内在住のエンジニアが在宅勤務を行う場合、以下の体制を整備し、社内規程として明文化することが極めて重要です。
- 客観的な労務管理体制の構築 勤怠管理システムやPCのログ記録など、客観的な方法で労働時間を把握する仕組みは必須です。加えて、日報や週報、プロジェクト管理ツールなどを活用し、「いつ、どのような業務を行っていたか」という活動内容を可視化できる体制を整えましょう。
- 明確な指揮命令系統とコミュニケーション 物理的に離れていても、誰が、どのように業務指示を行うのかという指揮命令系統を明確にする必要があります。定期的なWeb会議やビジネスチャットの活用ルールを定め、円滑な意思疎通と業務連携が取れる環境を構築し、それを対外的に説明できるようにしておくことが求められます。
- 規程・契約書への明記 上記のようなルールは、「リモートワーク規程」として具体的に定めます。また、雇用契約書においても、勤務地に「自宅」を含めることや、テレワークを許容する旨を明記するなど、実態に即した内容に見直すことが不可欠です。
ハイブリッド勤務(出社と在宅の組み合わせ)は、出社による物理的な勤務実態があるため、フルリモートに比べて企業の管理下にあると説明しやすい傾向にあります。しかし、その場合でも上記の体制整備は同様に重要です。
【海外編】海外からのリモートワークにおける課題
日本企業の従業員が海外からリモートワークを行う場合、日本の在留資格制度の直接的な管理下からは外れます。そのため、直ちに在留資格が取り消されるわけではありませんが、将来的なビザ更新や、企業の法務・税務面で下記のような重大な課題が生じます。
- 在留資格更新への影響 在留期間の更新申請は、本人が日本国内にいる必要があります。海外滞在が長期化すると、更新のために必ず帰国が必要です。また、日本国内での活動実績が乏しいと判断された場合、更新が許可されても在留期間が「1年」など短期になる可能性があります。出国時には、みなし再入国許可の期限(1年)にも注意が必要です。
- 在留資格「以外」の法的リスク むしろ、企業が直面する真の課題はこちらにあります。
- 現地の就労ビザ: 業務を行う国の法律に基づき、その国での就労許可が別途必要になる可能性が非常に高いです。
- 国際税務: 日本と現地国での二重課税のリスクが生じ、納税に関する複雑な問題が発生します。
- 社会保険: 二国間の社会保障協定に基づき、どちらの国の制度が適用されるか専門的な判断が求められます。
これらの課題は現地の法律が絡むため、見過ごすと深刻なコンプライアンス違反に繋がりかねません。
まとめ
外国人ITエンジニアのリモートワークは、企業のグローバルな人材戦略において有効ですが、在留資格制度の正しい理解と、それに基づいた労務管理体制の構築が成功の前提となります。特に海外からのリモートワークは、税務や各国のビザなど、日本の在留資格以外の法的リスクにも目を向ける必要があります。
こちらの記事ではより詳細に説明をしています。是非ご確認ください。