【2025年10月改正】在留資格「経営・管理」の基準厳格化と今後の更新対策
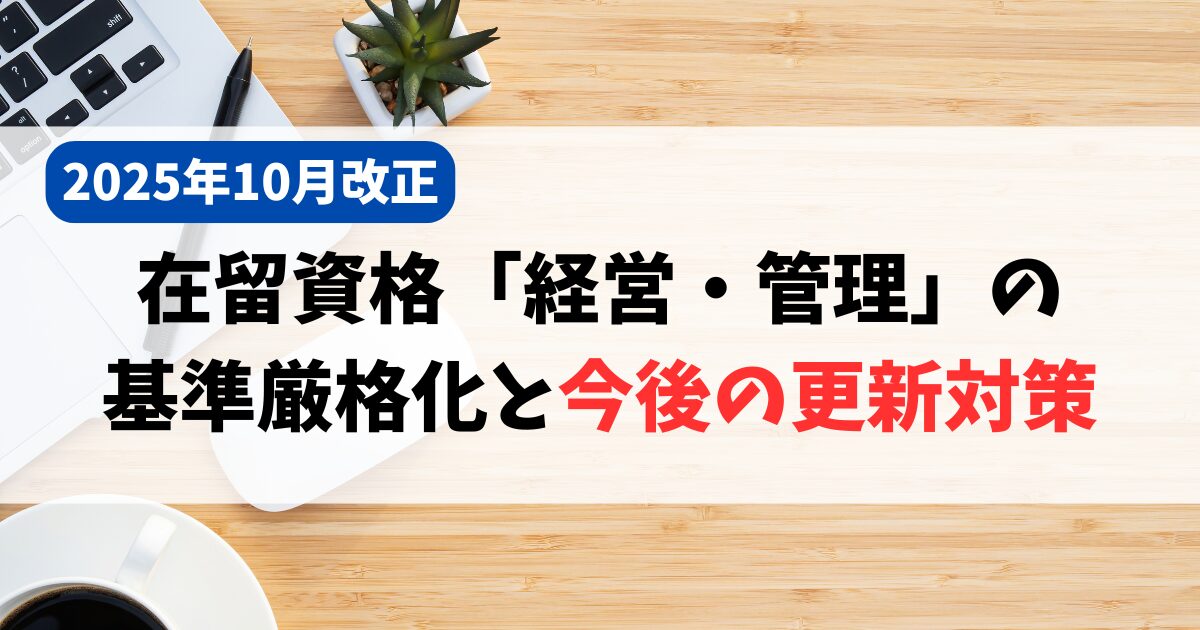
2025年10月16日、在留資格「経営・管理」の許可基準が大幅に改正されました。この変更は、新規申請者のみならず、現在「経営・管理」の在留資格で日本に在留されている皆様のビザ更新に直接関わる、極めて重要なものです。
本記事では、今回の法改正の要点を整理し、特に在留資格の更新を控える経営者の皆さまが、今後3年間で何をすべきかを解説します。
▼弊所メディアでも詳しくご説明しております。よろしければこちらもご確認ください。
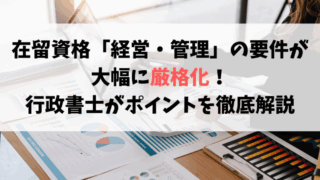
改正の要点:何が変わったのか?
今回の改正のポイントは、事業の実態や安定性・継続性を客観的な基準で厳格に審査するという点にあります。主な変更点は以下の通りです。
| 項目 | 旧基準 | 新基準 |
| 資本金・出資総額 | 500万円 | 3,000万円 |
| 経歴・学歴 | 特になし | 経営・管理経験3年以上 または 経営管理もしくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していること |
| 雇用義務 | 特になし(資本金の代替要件) | 常勤職員1名以上の雇用 |
| 日本語能力 | 特になし | 申請者または常勤職員が「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上 |
猶予期間が終わる2028年10月以降の申請については、「新基準」を満たしていなければ更新は認められません。
自己診断チェックリスト現状の確認と今後の課題
まず、ご自身の事業が、現在の時点で何をクリアし、今後3年間で何を準備すべきかを明確に区別することが重要です。
今回の法改正に伴って発表された、「次の更新から確認される既に経営者として必要な事項」と「3年の猶予期間内で満たさなければならない事項」に分けて、現状を客観的に確認してみましょう。
次の更新から確認される既に経営者として必要な事項
以下の項目は、今回の法改正に関わらず、健全な事業運営を行う上で当然に求められる基本事項です。もし「いいえ」があれば、新基準への対応以前に、事業の信頼性に関わる重大な問題となりますので、直ちに対応が必要です。
- 経営者としての活動実態 経営者として実態のある活動を行っていますか?(業務の丸投げなどを行っていないか)
- 在留状況 正当な理由なく、長期間日本から出国していませんか?
- 公租公課の履行 税金、社会保険、労働保険などを適切に納付していますか?
- 独立した事業所 事業所は自宅と完全に分離された、独立した区画を確保していますか?
- 許認可の取得 事業に必要な許認可をすべて取得していますか?
3年の猶予期間内で満たさなければならない事項
以下の項目は、今回の改正で新たに求められる、あるいは基準が引き上げられた要件です。「いいえ」と答えた項目が、経過措置期間である3年間で計画的にクリアすべき課題となります。
- 資本金・事業規模 資本金(または事業への投下資本)は3,000万円以上ですか?
- 経営者の経歴 ご自身に3年以上の経営経験、または関連分野の修士号以上の学歴がありますか?
- 常勤職員の雇用 日本人・永住者等の常勤職員を1名以上雇用していますか?
- 日本語能力 ご自身、または常勤職員は「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語力を有していますか?
次の章では、これらの課題を解決するための具体的なアクションプランを項目別に解説していきます。
更新を問題無く行うための具体的なアクションプラン
自己診断チェックリストで「いいえ」がある場合、在留資格「経営・管理」の維持(更新)ができなくなる可能性があります。
次の更新で満たしていなければならない項目、経過措置期間内に満たせばよい項目がありますが、これらの課題を計画的に解決するための貴重な時間です。以下に、各課題に対する具体的なアクションプランを解説します。
次の更新の前に行うべきアクションプラン
以下の項目は今まで以上に厳しく審査されるポイントです。次回のビザ更新から確認されると考えてください。
これらは新しいルールではありませんが、日本でビジネスをきちんと行っているかを示す、とても大切な基本です。新しい基準への対応を考える前に、まずはご自身の会社がこれらの基本をクリアしているか、必ず確認してください。
対策1:経営者としての活動実態の確保
日本で真剣に事業をされている多くの経営者の方にとって、この項目は問題にならないでしょう。
しかし、もし在留することだけが目的で、実態のない事業計画で来日し、これまで本格的な事業活動を行ってこなかった場合は注意が必要です。もし、まだ事業を本格的に始めていないのであれば、「すぐに日本で事業を本格化させる」か「事業をたたんで他の道を探す」かを決断する必要があります。
特に注意すべきは、今後の更新審査では、正当な理由なく長期間日本を離れていた場合、それ自体が更新不許可の理由になることです。日本で事業を経営する意思がないと判断されれば、在留資格を維持することはできません。
対策2:税金、社会保険、労働保険の適切な納付
これは法改正以前からの基本要件ですが、審査はより厳格化されています。法人税、法人住民税、消費税、源泉所得税などの国税・地方税はもちろん、代表者個人の住民税の支払いも審査対象です。
加えて、労働保険(雇用保険・労災保険)および社会保険(健康保険・厚生年金)への加入と、保険料の適切な納付は必須です。中には、コストを理由に加入していなかった法人もあるでしょう。社会保険に国籍は関係ありませんので、要件を満たしている事業所は加入していなければなりません。未納や遅滞がある場合は、在留資格の更新において重大な欠格事由となります。直ちに管轄の役所へ相談し、完納してください。
対策3:独立した事務所の確保
新基準では、事業の規模や実態に応じた独立した事業所が求められます。これまでは問題視されていなかった自宅兼事務所(住居の一部を事務所とする形態)は、今後は原則として認められなくなります。 バーチャルオフィスや、実態のないレンタルスペースも同様に不許可のリスクが非常に高いです。事業活動を行うにふさわしい独立した区画を確保し、賃貸借契約書や法人登記を整備しておく必要があります。
対策4:事業に応じた許認可の取得
日本で事業を行うには、その業種に応じた許認可(例:飲食店営業許可、宅地建物取引業免許、古物商許可など)が必要な場合があります。 これらの許認可を適法に取得・更新していることは、事業の適法性を示す上で不可欠です。万が一、必要な許認可を取得せずに事業を行っている場合、法令違反として更新は極めて困難になります。自社の事業内容を再確認し、必要な許認可がすべて揃っているかを確認してください。
3年の猶予期間内で行うべきアクションプラン
上記の基本に加え、以下の新基準への適合が求められます。3年間の経過措置期間は、これらの課題を解決するための準備期間です。
対策5:資本金3,000万円への増資計画
新基準では、事業の安定性を示す客観的な指標として、3,000万円の資本金(または事業への投下資本総額)が求められます。
- 資金調達の検討: 自己資金の投入、日本政策金融公庫等からの融資、あるいは第三者割当増資による出資の受け入れなど、具体的な資金調達計画を立て、実行に移す必要があります。
- 資金の出所証明の準備: 増資した資金の出所は、入管審査において厳しく確認されます。単なる「見せ金」と判断されないよう、送金記録や預金通帳の写し、金銭消費貸借契約書など、資金の形成過程を明確に証明できる客観的な資料を必ず保管してください。
対策6:経営者の経歴の証明
これまでは特に問われなかった経営者の経歴について、以下のいずれかを満たすことが新たに義務付けられました。
- 事業の経営または管理について3年以上の実務経験
- 経営管理または関連事業分野の修士号以上の学位
現時点で修士号が無い方でも、猶予が到来する3年以内には「事業の経営または管理について3年以上の実務経験」を満たすのではないかと思います。ちなみに、この「3年以上の職歴」には在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間も含みます。
対策7:常勤職員の採用計画
新基準では、原則として1名以上の常勤職員の雇用が義務付けられます。
- 採用対象の確認: 雇用すべき「常勤職員」は、日本人、特別永住者、または「永住者」「日本人の配偶者等」といった身分系の在留資格を持つ外国人に限られます 。「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労ビザを持つ外国人はこの要件の対象外ですので、採用の際は注意が必要です。
- 採用活動と手続き: ハローワークや人材紹介会社を活用し、計画的に採用活動を進めてください。採用後は、雇用契約書を締結し、労働保険・社会保険の加入手続きを速やかに行う必要があります。
対策8:日本語能力の確保
経営者ご自身、または常勤職員のいずれかが、一定水準(「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上)の日本語能力を有することが必要になります。
具体的には以下のいずれかに該当している必要があります。
・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・ 中⾧期在留者として20年以上我が国に在留していること
・ 日本の大学等高等教育機関を卒業していること
・ 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
まとめ
今回の法改正は、日本で真剣に事業を行う経営者にとっては、自社の信頼性をより強固にする好機とも言えます。
3年という時間は限られています。更新直前になって慌てることのないよう、早い段階からご自身の状況を客観的に把握し、計画的に準備を進めることが不可欠です。
当事務所では、今回の法改正に関するご相談を随時受け付けております。個々の状況に合わせた最適な更新プランの策定から申請代行まで、専門家がサポートいたしますので、少しでもご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

