【2025年法改正】特定技能「5年の壁」に救済措置が新設!在留延長の要件を専門家が解説

企業の皆様にとって、外国人材の確保と定着は重要な経営課題です。特に「特定技能」制度は多くの業界で活用されています。これまで、特定技能1号の在留期間は最長5年とされ、その間に上位資格である2号の試験に合格できなければ、優秀な人材も帰国せざるを得ない「5年の壁」がありました。
しかし、この状況を大きく変えるルール改正が行われ、特定技能2号の試験に惜しくも不合格となった方のための「救済措置」が新設されました。
本記事では、この新しい救-済措置について、誰が対象で、どのような要件が必要なのかを専門家の視点から分かりやすく解説します。
1.特定技能1号と2号の違い
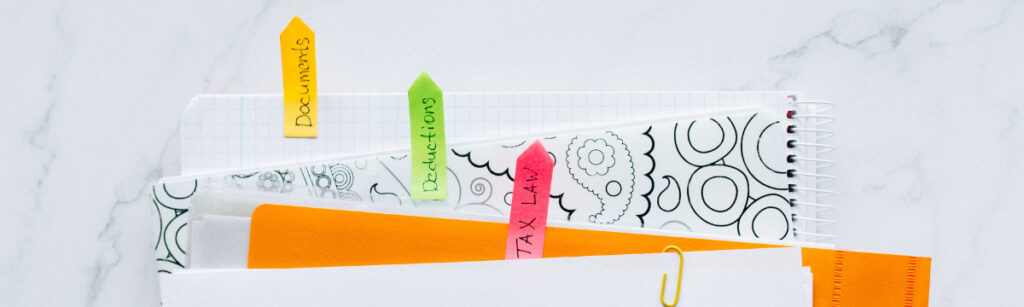
新しい救済措置を理解するために、まずは特定技能制度の基本である「1号」と「2号」の違いを簡単におさらいしておきましょう。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 在留期間 | 通算で上限5年 | 上限なし(更新可能) |
| 技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
| 家族の帯同 | 原則として不可 | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
| 対象分野 | 12分野 | 1号の対象分野のうち11分野 |
このように、特定技能2号は在留期間の上限がなく、家族の帯同も可能になるなど、外国人材が日本で長期的にキャリアを築いていくための重要なステップとなります。そのため、多くの1号特定技能外国人の方が、在留期間中に2号への移行を目指して試験に挑戦しています。
これまでの課題「5年の壁」

しかし、前述の通り、これまでは大きな課題がありました。それが「5年の壁」です。
特定技能1号の在留期間は、更新を重ねても通算で最長5年です。この5年の間に特定技能2号の試験に合格し、在留資格の変更許可を得なければ、原則として帰国するしかありませんでした。
2号試験の受験資格に「実務経験」の要件をクリアしていることなどがあり、分野によっては試験に挑戦できる回数も限られ、また、受験する試験によってはとても難易度が高い試験もあります。試験に合格できなければ5年でキャリアが途絶えてしまう。これは、ご本人にとってはもちろん、育成してきた企業にとっても、非常にもったいない状況でした。
【本題】新設された救済措置とは?
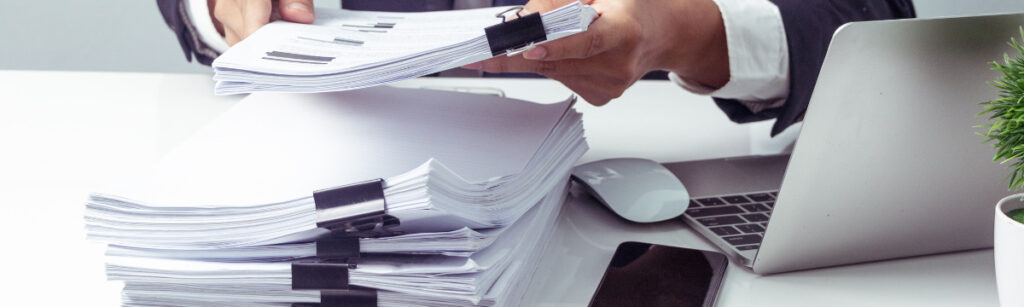
こうした課題を背景に、今回新設されたのが「特定技能2号評価試験等に不合格となった場合の救済措置」です。この制度を一言で表すなら、「試験合格まであと一歩だった優秀な人材に、企業と本人が一体となって再挑戦するチャンスを与えるための、厳格な条件付きの特例措置」と言えます。
この措置を利用することで、特定技能1号の通算在留期間5年の上限を超えて、最大で合計6年まで在留期間を更新できる可能性が出てきました。つまり、試験に再挑戦するための準備期間として、新たに1年間の在留が認められるのです。
ただし、これは不合格者全員が自動的に対象となるわけではありません。非常に厳格な要件が定められており、それらを全てクリアする必要があります。次に、その具体的な要件を詳しく見ていきましょう。
救済措置を利用するための4つの重要要件

この特例を利用するためには、外国人本人と雇用企業の双方に、以下の要件を満たすことが求められます。
外国人本人側の要件
(1)合格基準点の8割以上の得点を取得していること
これが最も重要かつ厳しい条件です。不合格になった2号試験で、「合格基準点の8割以上の得点を取得している」ことが絶対条件となります。 単に「不合格だった」というだけでは対象になりません。「合格まであと一歩だった」という客観的な証明が必要なのです。この得点率は、試験結果通知書などの疎明資料によって証明することになります。
(2)本人が3つの事項を誓約すること
得点率の条件をクリアした上で、ご本人は以下の3点を書面で誓約する必要があります。
- 必ず再受験すること: 延長された期間は、あくまで再挑戦のための期間です。合格に向けて努力し、必ず再度試験を受ける意思が求められます。
- 合格した場合は、速やかに「特定技能2号」へ変更申請すること: 目的は2号への移行ですので、合格したにもかかわらず変更申請をしない、といったことは認められません。
- もし再受験でも不合格だった場合は、速やかに帰国すること: これはあくまで1回限りのチャンスであり、再度の延長は認められないという厳しい約束です。この誓約があるからこそ、特例としての在留が認められます。
雇用企業(特定技能所属機関)側の要件
(3)申請人を引き続き雇用する意思があること
企業側にも意思表示が求められます。延長された期間中も、引き続きその外国人を雇用し、安定した就労環境を提供することが必要です。
(4)合格に向けた指導や研修を行う体制を整えること
単に雇用を継続するだけでなく、業務に関連する研修や勉強会の実施するなど、本人の試験合格を企業が積極的にサポートする体制が求められます。具体的には、以下のような取り組みが考えられます。
企業と本人が二人三脚で合格を目指す姿勢が、この制度利用の前提となっているのです。
申請手続きと最大の注意点

この特例を利用したい場合、5年の通算在留期間が満了する前(概ね3ヶ月前が目安)に、通常の在留期間更新許可申請を行います。その際に、これまでの提出書類に加えて、以下の書類を添付する必要があります。
- 通算在留期間を超える在留に関する申立書
- 合格基準点の8割以上の得点を取得していることが確認できる試験結果通知書の写し
これらの書類を提出し、出入国在留管理庁が「在留を適当と認めるに足りる相当の理由がある」と判断した場合に限り、通算在留期間6年を上限として在留期間の更新が許可されます。
【最重要】申請における最大の注意点
この制度を利用する上で、現時点で非常に大きな注意点があります。それは、「試験結果通知書に得点率や、それに準ずる情報が記載されていない場合がある」という点です。
本人側の要件(1)でご説明した通り、この特例の利用には「合格基準点の8割以上の得点」を客観的に証明する必要があります。しかし、試験分野によっては、現在の試験結果通知書に「合格/不合格」の記載しかなく、具体的な得点や得点率が分からないものがあるのです。
出入国在留管理庁も、得点率が確認できない試験結果通知書では、この特例は利用できないと明言しています。
現在、対象外となっている試験についても、今後は試験実施機関の準備が整い次第、対象となる可能性はありますが、申請を検討する時点では、必ずお手元の試験結果通知書で得点率が確認できるかどうかを第一にご確認ください。
まとめ

今回の法改正は、これまで「5年の壁」に阻まれてきた優秀な外国人材と、その人材を失いたくないと願う企業にとって、大きな希望となるものです。
もちろん、「合格まであと一歩」という高いハードルや、「企業と本人の一体となった努力」が求められる厳格な制度ではありますが、適切に活用すれば、人材の長期的な定着と企業の成長に大きく貢献するでしょう。

